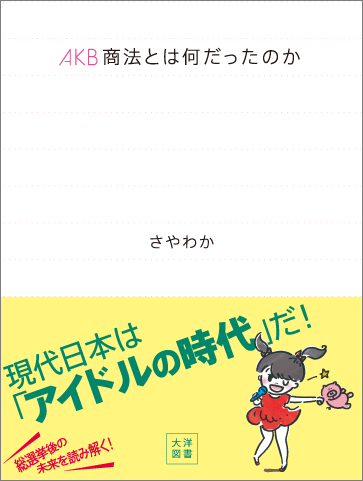『AKB商法とは何だったのか』を巡る、様々なコンテンツをお届けいたします。
村上裕一http://bonet.info にて毎日平日18:00頃から更新中@murakami_kun
『AKB商法とは何だったのか』
AKB48はなぜ批判されるのか? という疑問を発端に、「今のアイドル」や「今の音楽シーン」を語り尽くした『AKB商法とは何だったのか』。アイドルを批判も賞賛もせず、豊富な資料に基づいて日本の現状をじっくり考察した好著として各方面から評価されています。『僕たちのゲーム史』を巡る対談 も行なわれている村上さんですが、はたして本書はどのように受け止められたのでしょうか。
タイトル:AKB商法とは何だったのか